
2024年、新しいNISA制度の導入によって、日本の個人投資家を取り巻く環境は大きく変わりました。その中でも、「つみたてNISA」はより一層注目を集めています。
なぜ今、改めて“つみたて”が脚光を浴びているのか――。それは、誰にとっても資産形成の「最初の一歩」にふさわしい制度だからです。
これまで「投資は難しい」「自分にはまだ早い」と感じていた方でも、月1,000円から始められ、しかも20年という非課税期間を味方にできる。これほど“長期×少額×分散”の三拍子が揃った制度は、他にありません。
しかも、対象ファンドはすべて国が厳選した“長期運用にふさわしい投資信託”ばかり。どれを選んでも極端にハズレを引くリスクは小さく、投資初心者でも安心して取り組める仕組みになっています。
とはいえ、100本以上ある選択肢の中から「自分に合った1本」を選ぶのは、簡単ではありません。間違った選び方をしてしまえば、想定よりもリターンが出なかったり、運用を途中でやめてしまうリスクもあります。
この記事では、「つみたてNISAって結局どう選べばいいの?」「どのファンドを選べば失敗しないの?」という声に応えるべく、2025年最新情報をもとに、制度の解説からおすすめファンド、具体的な選び方までを丁寧に解説していきます。
第1章:つみたてNISAの制度を理解する ― 2024年改正ポイントと基本の仕組み

新NISA制度の概要と変更点(つみたて枠と成長投資枠)
まずは制度の全体像を押さえておきましょう。2024年にスタートした「新NISA制度」では、従来の「一般NISA」「つみたてNISA」という2制度が一本化され、「つみたて枠」と「成長投資枠」の2階建て構造になりました。
- つみたて枠:年間120万円まで(旧制度の2倍以上)、非課税期間は無期限
- 成長投資枠:年間240万円まで、主に個別株やETFなどが対象
- 生涯非課税投資枠:1,800万円(うち成長投資枠は1,200万円まで)
特に注目すべきは「非課税期間の無期限化」と「投資枠の拡大」です。これにより、つみたてNISAはより“長期資産形成”に特化した制度となり、中間所得層や将来の生活資金を重視する世代にとって、非常に魅力的な選択肢となっています。
非課税枠・年間投資額・対象者などの基本ルール
対象者は、日本国内に居住する18歳以上の個人で、口座は1人1口座に限定されます。年間の上限投資額は、「つみたて枠」で120万円、月額にすると最大で10万円まで。
購入できるのは、金融庁の定めた一定の要件を満たす長期投資向けの投資信託に限られており、販売手数料が無料(ノーロード)、信託報酬が一定水準以下であるなどの厳格な条件があります。
このように、「国が“あえて制限を設けている”」制度であることこそが、つみたてNISAの安心感につながっています。
なぜ「つみたてNISA」は初心者に向いているのか?
最大の理由は、「シンプルさと自動化の仕組み」にあります。
投資信託を毎月自動で積み立てられるうえ、価格のタイミングを気にする必要もありません。いわゆる「ドルコスト平均法」が自然と実践できるため、高値づかみのリスクも分散されます。
また、非課税メリットが極めて大きいため、「毎年の税金計算が面倒…」といった心配も不要。運用益が出た場合も、売却時に20.315%の税金を差し引かれることなく、利益をそのまま受け取れるのです。
つまり、「投資に詳しくないけど始めてみたい」「将来に備えた資産形成がしたい」という方にとって、これほど適した制度は他にないと言っても過言ではないでしょう。
第2章:対象ファンドの選定条件 ― 国が定める「厳選された商品」の意味
つみたてNISA対象ファンドの選定基準(信託報酬・資産配分など)
つみたてNISAの対象ファンドになるには、金融庁が定めた厳格な基準を満たす必要があります。その中でも特に重視されているのが、以下の3点です。
- 信託報酬(運用コスト)が一定水準以下であること
- 販売手数料が無料(ノーロード)であること
- 長期・積立・分散投資に適した運用方針を持っていること
例えば、インデックスファンド(指数連動型)の場合、信託報酬が0.5%以下、純資産残高50億円以上などが条件とされています。これにより、長期的に安定して運用されている低コストファンドのみが対象となるのです。
アクティブファンドはなぜ少ない?条件の背景にある政策意図
つみたてNISA対象ファンドの大半がインデックス型で、アクティブファンドがごくわずかなのはなぜか――。その背景には、「長期投資における再現性と低コスト性」を重視する政策意図があります。
アクティブファンドは市場平均を上回ることを目指す一方で、手数料が高く、運用結果のブレが大きくなりがちです。初心者がリスクを正確に把握するのは難しく、途中で運用をやめてしまうケースも少なくありません。
そのため、つみたてNISAでは「誰にでも再現しやすく、長期で成果が出やすい投資信託」を中心に据えているのです。
対象ファンドは何本ある?2025年最新の本数と傾向
2025年時点で、つみたてNISAの対象ファンドは200本前後。そのうち約9割がインデックスファンド、残りが厳選されたアクティブファンドという構成です。
近年の傾向としては、全世界株式・米国株式を投資対象としたファンドの人気が急上昇しており、eMAXIS Slimや楽天・バンガード、SBI・Vシリーズなど、いずれも信託報酬が年0.1%前後と超低コストで運用されている商品が主力となっています。
このように、制度上の安心感だけでなく、市場トレンドを反映した商品ラインナップの充実も、つみたてNISAの魅力と言えるでしょう。
第3章:初心者でも失敗しない「ファンドの選び方」7つのチェックポイント
投資信託選びに正解はありませんが、一定の“判断軸”を持つことで、後悔のない選択に近づくことができます。ここでは初心者でも迷わず選べるように、7つの視点からチェックすべきポイントを整理していきましょう。
1. 手数料(信託報酬)の目安と「安さの違い」がもたらす影響
信託報酬は、保有している間ずっと発生し続けるコストです。たとえば、年間信託報酬が0.1%と0.5%の商品を比べると、一見わずかな差に見えますが、10年後には数万円以上の差になることも。
投資信託の選定では、信託報酬が0.2%以下をひとつの目安にするのが良いでしょう。eMAXIS SlimシリーズやSBI・Vシリーズなどは、優れたコストパフォーマンスを誇ります。
2. インデックス型 vs アクティブ型の違いと向き不向き
インデックス型は、TOPIXやS&P500などの指数に連動する運用を行うため、コストが低く、安定した長期運用が可能です。対して、アクティブ型は運用担当者が独自の判断で投資先を選定し、指数を上回るリターンを目指します。
ただし、アクティブ型は信託報酬が高く、成果にばらつきがあるため、初心者にはインデックス型の方が無難と言えるでしょう。
3. 投資地域(日本・米国・全世界)をどう選ぶか
「どの国や地域に投資するか」は、将来のリターンを大きく左右します。たとえば、
- 全世界株式(オール・カントリー):地球規模で分散投資。最も安定志向。
- 米国株式:過去20年間、高い成長率を誇る。ただし為替リスクも。
- 日本株式:身近な企業が多いが、成長性には限界も。
初心者には「全世界株式」か「米国株式」に絞るのがおすすめです。どちらも信頼性の高いインデックスが存在し、つみたてNISAの主力商品にもなっています。
4. 純資産残高と運用実績はどの程度重視すべきか?
純資産残高は、その投資信託がどれだけの資金を集めているかの指標です。目安としては100億円以上あると安定運用が期待できます。また、長期間にわたって運用実績が良好なファンドは、信頼度が高いと言えるでしょう。
ただし、できたばかりの優良ファンドが悪いというわけではありません。比較する際は、同じカテゴリーの商品と「信託報酬」「組入銘柄」「ベンチマークとの乖離」などを合わせて確認すると良いでしょう。
5. 運用会社の信頼性・継続性も判断材料
運用会社の知名度だけで判断するのは避けたいですが、「長期的に安定した運用をしてきたか」「低コスト路線を継続しているか」は重要な指標です。
たとえば、三菱UFJアセットマネジメント(eMAXIS Slim)、SBIアセットマネジメント、バンガードなどは、投資家ファーストの姿勢を評価されています。
6. 自動積立の設定・使い勝手(証券会社選びも含めて)
ファンドそのものが良くても、積立設定が使いにくければ続けるのが難しくなります。SBI証券、楽天証券、マネックス証券などのネット証券は、画面がシンプルで、積立頻度や金額も柔軟に設定できるのが魅力です。
特に「毎日積立」「ボーナス月設定」「ポイント利用」などが可能かどうかも、継続のしやすさに関わってきます。
7. 自分の投資目的・ゴールに沿った商品か?
最後に見落としがちなのが「投資目的との整合性」です。単に人気ランキングに従うのではなく、「自分は老後資金を作りたいのか」「教育資金を準備したいのか」といった目的に応じてファンドを選ぶことが大切です。
目的が明確であれば、多少価格が下がってもブレずに積立を継続できるはずです。
第4章:2025年注目!つみたてNISA対象のおすすめファンド10選

ここでは、読者の皆さんがすぐに参考にできるよう、2025年時点で評価の高いつみたてNISA対象ファンドを厳選してご紹介します。いずれも「低コスト・長期投資向け・初心者向け」という条件を満たしており、投資初心者でも安心して選べる商品です。
【1】eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
- 信託報酬:年0.1133%
- 対象地域:全世界(日本含む)
- 特徴:地球全体にまんべんなく投資。最も安定志向で“ほったらかし投資”向き。
【2】楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天VTI)
- 信託報酬:年0.162%
- 対象地域:米国(VTIに連動)
- 特徴:米国経済全体に投資できるシンプルな構成。成長性と安定性のバランスが良好。
【3】SBI・V・S&P500インデックス・ファンド
- 信託報酬:年0.0938%
- 対象地域:米国(S&P500)
- 特徴:圧倒的低コスト。米国を代表する500社にまとめて投資。
【4】たわらノーロード 先進国株式
- 信託報酬:年0.10989%
- 対象地域:米国・欧州を中心とした先進国
- 特徴:米国以外も視野に入れた分散投資が可能。バランス型の位置づけ。
【5】iFreeNEXT NASDAQ100インデックス
- 信託報酬:年0.495%
- 対象地域:米国(NASDAQ100)
- 特徴:テクノロジー・グロース企業中心。リターンは大きいが変動性も高い。
【6】eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
- 信託報酬:年0.09889%
- 対象地域:先進国全体
- 特徴:王道の1本。コスト・分散性・実績のバランスが極めて良い。
【7】ニッセイ外国株式インデックスファンド
- 信託報酬:年0.1023%
- 対象地域:先進国株式
- 特徴:長年の運用実績あり。低コストで安定感抜群。
【8】ひふみプラス(アクティブ型)
- 信託報酬:年1.078%
- 対象地域:日本株中心(一部海外)
- 特徴:唯一のアクティブ型。運用者の顔が見える。支持層も厚い。
【9】コモンズ30ファンド
- 信託報酬:年1.078%
- 対象地域:日本株中心
- 特徴:「社会的価値」と「長期成長性」を重視。共感投資型。
【10】iTrust世界株式(高配当志向)
- 信託報酬:年0.99%
- 対象地域:全世界
- 特徴:配当も意識したファンド。中長期のインカムゲインを狙いたい人向け。
それぞれの商品に特色がありますが、「まずは1〜3本に絞って積み立てを始める」というのが現実的な選択です。次章では、「失敗しやすい選び方とその回避策」について深掘りしていきます。
第5章:初心者が注意すべき3つの落とし穴と回避策
つみたてNISAは初心者にもやさしい制度設計になっているとはいえ、「ついついやってしまいがちな失敗」がいくつかあります。ここでは、よくある3つの落とし穴と、それを避けるための実践的なアドバイスをご紹介します。
1. 人気ランキングだけで選ぶのは危険!
「とりあえず1位だから」「YouTubeで話題になっていたから」という理由で選ぶのは要注意です。ランキングは直近の成績や話題性を反映するものに過ぎず、自分の投資目的やリスク許容度と合っていないケースも。
例えば、NASDAQ100連動型のファンドは高いリターンが期待できますが、変動幅が大きく、下落時に不安で解約してしまう人も少なくありません。
対策としては、「なぜこのファンドが自分に合っているのか」を言語化してみること。それが難しい場合は、全世界株式のような“守備力の高いファンド”から始めてみるのが安全です。
2. リターン“過去実績”に振り回されない判断軸とは?
「過去5年で+◯%」という実績は、参考にはなりますが、将来のリターンを保証するものではありません。むしろ、過去の成績が良すぎるファンドには“反動”が来る可能性も。
本当に見るべきは、「どういった資産に投資しているか」「それがどのような経済環境でリターンを出してきたか」といった背景です。地道でも堅実な構成かどうかが、長期投資では成功の鍵になります。
3. 分配金がない=損?誤解されやすい仕組みを正しく理解する
「このファンド、配当金が出ないから損では?」と思われがちですが、つみたてNISAの多くのファンドは分配金を出さずに“自動再投資”する仕組みになっています。
この方式のメリットは、税金を繰り延べつつ“複利”で資産が増えていくこと。配当を受け取ってその都度使うよりも、運用効果が高くなる可能性があります。
「配当金=お得」と短絡的に考えず、資産全体の成長性でファンドを評価することが大切です。
第6章:証券口座の選び方と積立設定のステップ解説
ファンドを選んだら、次は「どこで買うか」「どう積み立てるか」という実践フェーズです。ここでも“始めやすく、続けやすい環境”を選ぶことが、継続のカギになります。
つみたてNISA対応おすすめ証券会社ランキング
以下の3社は、つみたてNISAにおいて非常に使い勝手が良く、多くの利用者に選ばれています。
| 証券会社 | 特徴 |
|---|---|
| SBI証券 | 取扱ファンド数が圧倒的。Tポイント/クレカ積立対応。手数料無料で優秀なネット証券 |
| 楽天証券 | 楽天ポイントが使える&貯まる。楽天経済圏ユーザーに相性抜群 |
| マネックス証券 | 米国株にも強み。クレカ積立でマネックスポイントが貯まる |
これらの証券会社はいずれもスマホアプリが使いやすく、投資初心者にもやさしい設計になっています。
積立設定の画面やステップをやさしく紹介
実際の積立設定は、以下の流れで完了します(例:SBI証券)。
- 口座開設(マイナンバー提出含む)
- 「つみたてNISA口座」に切り替え申請(初回のみ)
- ファンドを検索 →「つみたてNISA対象」のチェックをオン
- 月額・積立日・支払い方法(銀行引落またはクレカ)を設定
- 確認して完了!毎月自動で積立開始
これだけです。特に設定画面はシンプルで、スマートフォンからでも5分程度で完了できます。
自動化で投資を「習慣」にする仕組みづくり
資産形成において、最も重要なのは「投資を続けること」です。どれだけ良いファンドを選んでも、途中でやめてしまえば意味がありません。
そのためには、「生活の中で自然に積み立てられる仕組み」を作ることがカギ。給料日翌日に自動引き落とし、ポイント利用、年1回の見直しなど、自分に合ったルールを作っておくと、ストレスなく継続できます。
まとめ:最も大切なのは「自分の目的と相性の良いファンド」を選ぶこと
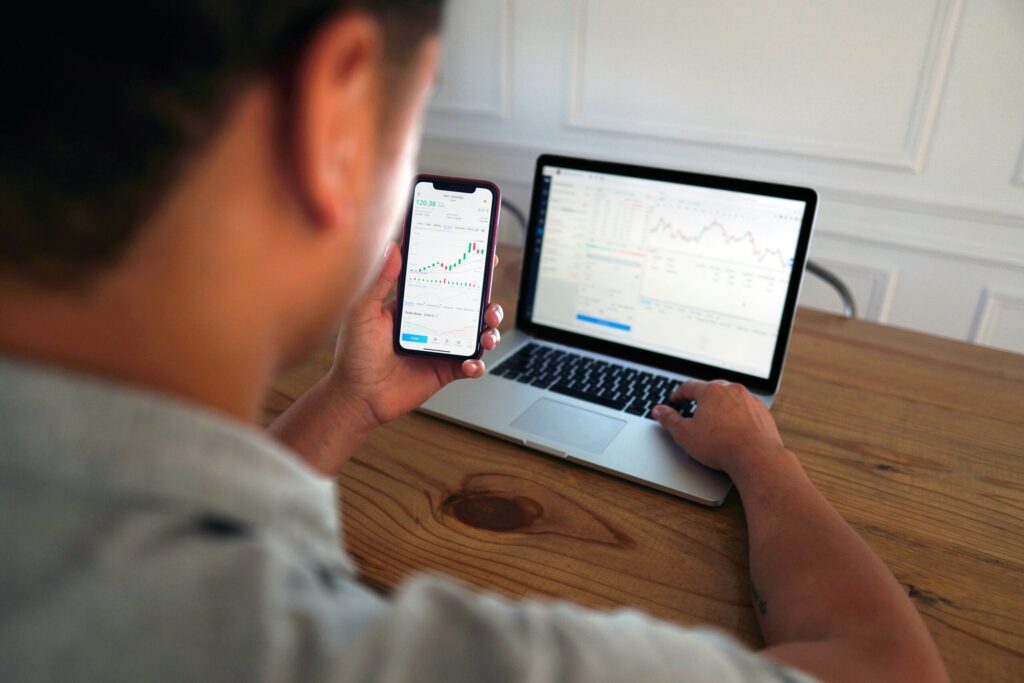
ここまで、つみたてNISAの制度の仕組みから、ファンドの選び方、おすすめ商品、さらには口座開設・積立設定までを詳しく解説してきました。
おそらく、記事を読み進めてくださったあなたは、「結局、どれを選べばいいの?」という疑問に対して、ある程度の手応えを感じているのではないでしょうか。
しかし、最後にもう一度強調しておきたいのは、「誰かにとっての正解が、あなたにとっての正解とは限らない」ということです。
商品選びに“絶対の正解”はない
つみたてNISAで用意されているファンドは、どれも金融庁が定めた厳格な基準を満たした、信頼性の高い商品ばかりです。その中で、さらに「より良いもの」「もっとリターンが期待できそうなもの」を求める気持ちはよくわかります。
でも、本当に重要なのは「自分がなぜ投資を始めるのか」「どんなゴールを目指しているのか」という“目的”を明確に持つこと。そしてその目的に合った商品を、納得して選ぶことです。
資産運用とは、単なるお金の増減を超えた、“生き方の選択”でもあります。
少額からでも「始めること」が最大のアクション
どれだけ多くの情報を集めても、実際に始めなければ資産は1円も増えません。たとえ月1,000円でも、1年後・10年後には驚くほどの差が生まれます。
積立投資は「時間と継続」が最大の武器。迷っている間にも、マーケットは動き続けています。
まずは一歩踏み出すこと。そこから、あなたの投資人生は確実に動き出します。
「選んで、積んで、忘れる」くらいがちょうどいい
投資初心者にとっては、「日々の値動きに一喜一憂してしまう」のが最大の落とし穴かもしれません。
でも、つみたてNISAはそうした短期的な感情を排除し、“放っておける仕組み”をあえて作り上げた制度です。
だからこそ、「選んで、積んで、忘れる」。そんなシンプルな姿勢で取り組むことが、長期的にはもっとも合理的で、もっとも成功に近づく方法なのです。
最後にひとこと
つみたてNISAは、ただの制度ではありません。あなたの未来を、経済的に、そして精神的にも支えてくれる“資産形成のパートナー”です。
この制度をうまく活用し、ぜひあなたらしい投資スタイルを築いてください。あなたの一歩が、未来の安心を作るきっかけになることを、心から願っています。

ファイナンス専門ライター / FP
資産運用、節税、保険、財産分与など、お金に関する幅広いテーマを扱うファイナンス専門ライター。
金融機関での勤務経験を活かし、個人投資家や経営者向けに分かりやすく実践的な情報を発信。特に、税制改正や金融商品の最新トレンドを的確に捉え、読者の資産形成に貢献することを得意とする。





