
「愛があれば、お金なんて関係ない」。そんな言葉が美しく響くのは映画の中だけかもしれません。現実の結婚生活は、日常の細やかな選択と経済的な意思決定の連続です。
新婚生活のスタートは、まさに人生の分岐点。将来の家族計画や住まい、キャリアの方向性といった多くのライフイベントに備えるには、“感情”だけでなく“数字”との対話が欠かせません。
夫婦というチームで人生を歩んでいく以上、「二人でお金の話をすること」は愛情と同じくらい重要なコミュニケーション。だからこそ、今から“人生の設計図=資産形成”を描き始めることには、何よりも大きな意味があるのです。
「収入があるだけ」では足りない時代へ
かつては、「定職に就いて、コツコツ貯金していれば安泰」という時代が確かに存在しました。ところが現代は、長寿化、物価上昇(インフレ)、年金制度の不透明性といった、将来の見通しが立ちにくい時代に突入しています。
さらに、30〜40代の平均年収層においても、可処分所得の減少や増税への不安、住宅ローンの長期化など、多くの経済的プレッシャーを抱えているのが現実です。
収入があるだけでは、将来の安心は手に入りません。「資産をつくる」「守る」「育てる」この3つを、今から地道に積み重ねていく必要があります。
なぜ今から?新婚期こそ資産形成スタートに最適な理由
結婚直後は、家計がまだ複雑化しておらず、出費やライフスタイルの軌道修正も比較的しやすい時期です。この段階から夫婦でお金の価値観を共有し、資産形成の方針を立てておくことが、後々の人生設計を大きく左右します。
また、新婚期は以下のような「資産形成に最適な条件」が整っています:
- ダブルインカム(共働き)による収入安定
- 子どもがまだいないケースが多く、生活コストが比較的低い
- 貯蓄や投資に“使えるお金”の自由度が高い
- 金融制度(つみたてNISA、iDeCoなど)を長期で活用できるスタート地点
つまり、結婚は単なる「家族の始まり」ではなく、「資産をともに育てるパートナーシップ」の出発点でもあるのです。
第1章:共働きor片働き?最初に整えるべき“家計の地盤”

「世帯収支の統合」と「使途明確化」で資産のブレを防ぐ
「お金の管理はそれぞれで」「お互いの口座はあまり知らない」——こうした“なんとなくの家計”は、新婚夫婦に多く見られるパターンです。しかし、資産形成の視点から見ると、非常に危うい状況と言えるでしょう。
まず重要なのは、世帯単位での「収入と支出」の可視化。夫婦どちらの収入がいくらあるか、固定費はどれだけかかっているのか、変動費は何に使われているのか。この情報が明確になることで、無駄な支出や重複した契約(例:サブスクや保険など)を把握でき、資産形成の“地盤”が固まります。
さらに、夫婦間でお金の「使途」を事前にすり合わせることも極めて重要です。
たとえば、こんな分け方が考えられます:
- 生活費(共通口座):食費・家賃・光熱費など
- 個人費用(個別口座):趣味・交際費・衣類など
- 貯蓄・投資(目的口座):将来資金・教育費・住宅資金など
収入を“見える化”し、目的別に分けるだけで、驚くほど支出の無駄が減ります。最初のひと手間が、数年後の資産差となって現れるのです。
貯蓄・支出・投資の“黄金バランス”
理想的な家計のバランスとして、一般的によく引用されるのが「収入の50:30:20ルール」。これは、以下のような配分を意味します:
- 50%:生活費(固定費+変動費)
- 30%:自由に使える支出(娯楽・外食・趣味)
- 20%:貯蓄・投資
ただし、これはあくまで参考値。共働きで収入が安定している家庭であれば、貯蓄・投資の比率を**30〜35%**まで引き上げることも可能です。
逆に、片働きで育児や住宅ローンの負担が重い家庭は、まず“生活防衛資金”を確保した上で、無理のない投資比率を模索することが重要です。
最も避けたいのは、「とりあえず残ったら貯金」という“後回しの資産形成”。貯蓄と投資は「先取り」が鉄則です。これはどんな世帯にも共通する黄金律だと言えるでしょう。
家計簿アプリ vs エクセル管理:成功している夫婦の選択肢とは
資産形成において「家計管理」は避けて通れません。ただ、問題は「何で管理するか?」という点。
現在は多くの人がスマホで使える家計簿アプリ(例:マネーフォワードME、Zaimなど)を活用しています。これらは銀行口座・クレジットカードと自動連携でき、視覚的にも分かりやすいのが魅力です。
一方で、エクセル(またはGoogleスプレッドシート)派も根強く存在します。こちらは自由度が高く、細かな分類やシミュレーションに強いため、投資・資産管理と連動したカスタム設計が可能です。
✔ どちらにもメリット・デメリットがあるため、まずは1〜2ヶ月使ってみて、夫婦のライフスタイルに合ったツールを選ぶのがベストです。大切なのは、「ツールを使うこと」ではなく、「家計を日々チェックする習慣」をつけることにあります。
第2章:「貯める力」こそ資産形成のエンジン
月収の何%?“理想の貯蓄率”とライフステージ別シミュレーション
資産形成というと、投資に意識が向きがちですが、土台となるのは「貯める力」。
しっかりとした貯蓄があることで、投資リスクを恐れず、ライフイベントにも柔軟に対応できる“余白”が生まれます。
では、どのくらい貯めるのが理想的なのでしょうか?
ファイナンシャルプランナーの多くが推奨するのは、月収の20〜30%の貯蓄率。
これは年収600万円の家庭なら、年間で144〜216万円の貯蓄となります。
ただし、ライフステージによって「貯蓄に回せる余力」は変化します。以下は一例です:
| ライフステージ | 推奨貯蓄率 | 貯蓄の目的 |
|---|---|---|
| 新婚期(20〜30代) | 30% | 住宅資金、教育資金、老後資金の土台 |
| 子育て初期 | 10〜20% | 教育費、生活費の増加対応 |
| 教育費ピーク(高校・大学) | 5〜10% | 学費への対応が最優先 |
| 子ども独立後 | 20〜30% | 老後資金・セカンドライフ準備 |
こうして見ると、新婚期こそ“貯蓄効率”がもっとも高いタイミングであることがわかります。
だからこそ、この時期に「貯める仕組み」を習慣化できるかどうかが、将来の安心感を左右するのです。
先取り貯蓄は「自動化」と「分散」がカギ
「お金を使ったあとに残った分を貯金する」。これは一見、堅実な考え方に思えますが、実際は“残らない”ことの方が多いものです。
そこで有効なのが「先取り貯蓄」です。
給与が振り込まれた瞬間に、自動で貯蓄や投資用口座に資金を移す仕組みをつくることで、「意志力」に頼らずに資産形成が進んでいきます。
たとえば、以下のような自動化が可能です:
- 銀行の定額自動送金設定(毎月●日に貯蓄口座へ送金)
- 証券会社の積立設定(つみたてNISAなど)
- 給与天引き型の企業型DC(確定拠出年金)や財形貯蓄制度
また、「貯蓄の分散」もリスク分散として非常に重要です。
仮に月10万円の貯蓄をする場合、以下のように配分する方法も検討に値します。
| 用途 | 金額 | 方法 |
|---|---|---|
| 生活防衛資金 | 30,000円 | 普通預金口座(緊急時に備える) |
| 将来の大型支出 | 40,000円 | 定期預金や積立定期など(住宅頭金、出産費用) |
| 長期資産形成 | 30,000円 | つみたてNISAやiDeCoなど投資に回す |
このように「使途別」に口座や方法を分けることで、漠然とした不安から脱し、貯蓄が“目的あるお金”へと変わっていきます。
預金だけじゃもったいない?“貯蓄性のある制度”の活用
「貯金しても利息はつかない」。これは誰もが感じている現代のリアルです。
大手都市銀行の普通預金金利は、2025年現在で年0.001〜0.02%程度。100万円を預けても、1年後の利息はわずか10円〜200円です。
そこで視野に入れたいのが、“貯蓄性のある制度”の活用。以下のような選択肢があります:
✅ 企業型DC(確定拠出年金)
企業が導入している場合、給与から天引きで積立投資が可能。
最大の特徴は掛金が全額所得控除の対象になるという税制優遇。
- 年収600万円で年間27.6万円の拠出 → 約6〜7万円の所得税・住民税軽減効果も期待
- 60歳まで引き出せないが、その分「確実に将来資産に変わる」仕組み
✅ 財形貯蓄制度
会社員向けの制度で、給与天引きによる自動貯蓄。住宅財形・年金財形など目的別に分けられ、利息非課税の優遇措置も。
- 溜まるスピードが速い(無意識に積み上がる)
- 手をつけにくく、堅実な貯蓄体質を形成できる
✅ 共済貯金・共済年金
公務員・教職員・一部の団体職員向けに用意された制度。
民間の預金よりも高い利率(1%前後)が設定されている場合があり、手堅い選択肢のひとつ。
このような制度は“目立たないけれど効果が大きい”存在です。
給与明細や就業規則を一度見直して、自分が使える制度を漏れなく把握しておきましょう。
第3章:投資初心者夫婦のための“やさしい資産運用”
株?投信?まずは「つみたてNISA」と「iDeCo」から始めよう
「投資を始めるって、ちょっと怖い」「失敗したらどうしよう」。
そんな気持ちは、ごく自然なものです。特に、家族というチームで資産を守り、増やしていく立場に立つと、慎重になるのは当然でしょう。
ですが現代では、“失敗しにくく、かつ始めやすい制度”が整ってきているのです。
その代表が「つみたてNISA」と「iDeCo」。これらは“初心者向けの制度設計”がされており、なおかつ税制面で非常に有利なため、新婚夫婦の資産形成にはまさにうってつけの選択肢といえるでしょう。
✅ つみたてNISA(2024年改正版)
- 年間最大120万円(非課税投資枠)
- 非課税期間は“無期限”(旧制度は20年まで)
- 月1万円〜など少額から始められる
- 金融庁が認可した“長期・分散・低コスト”な投資信託のみ対象
要するに、「ちゃんと選ばれた安心な投資商品を、無税でコツコツ育てていける制度」。
夫婦でそれぞれ口座を持てば、年間240万円分の投資に対して、運用益が一切非課税になります。
✅ iDeCo(個人型確定拠出年金)
- 月額23,000円(会社員・公務員)〜68,000円(自営業)まで拠出可能
- 掛金は“全額所得控除”→ 節税メリットが大きい
- 60歳まで原則引き出し不可(“老後専用の資産形成”)
つみたてNISAが「いつでも引き出せる資産」なのに対し、iDeCoは“老後資金に特化”しているのが大きな特徴。
運用益が非課税になるうえに、掛金も控除対象になるため、“節税しながら将来資産を育てる”二重のメリットが得られます。
投資信託の選び方:インデックス vs アクティブの違いとは
「じゃあ、つみたてNISAやiDeCoで何を買えばいいの?」という疑問に直面する方も多いでしょう。
ここでよく出てくるのが「インデックスファンド」と「アクティブファンド」という2つのタイプです。
| ファンドタイプ | 特徴 | 向いている人 |
|---|---|---|
| インデックスファンド | 日経平均やS&P500など、市場全体に連動 | 初心者、手堅くコツコツ増やしたい人 |
| アクティブファンド | 運用のプロが積極的に銘柄を選定 | リターンを狙いたいがリスクも許容できる人 |
初心者夫婦におすすめなのは、まずはインデックス型。
理由は明快で、「コストが低く、成績が安定しているから」。
たとえば、「eMAXIS Slimシリーズ」「楽天・全米株式インデックスファンド」などは、長期投資との相性が良く、実績も十分です。
年利3〜5%を実現する「長期・積立・分散」戦略の設計図
「投資って、うまくいっても1〜2%くらいなんでしょ?」と思われがちですが、実は違います。
正しく設計された投資は、年平均3〜5%の利回りを現実的に狙うことができます。
ではその“正しく設計された投資”とは何か?
キーワードは以下の3つです:
- 長期:10〜20年というスパンで時間を味方につける
- 積立:毎月一定額を購入し、市場の上下に影響されにくくする
- 分散:特定の銘柄に偏らず、複数の資産に分けて投資する
この戦略は、特別な知識やタイミングの見極めが不要なため、日々忙しい夫婦でも続けやすいのが最大の強みです。
仮に、月3万円を年5%で20年間運用した場合、元本720万円に対して、最終的な資産は約1,230万円に達します(複利効果による)。
ワンポイント:夫婦で投資を学ぶ習慣をつくる
最後に、実際の投資行動と並んで重要なのが、「夫婦で学び合う」文化です。
投資は“知識のある者だけがリスクを減らせる”分野です。そして、知識は「二人で共有」するからこそ、より強固になります。
- 月1回の“お金の作戦会議”を開催する
- 一緒に投資系の本や動画を視聴する
- 買付銘柄の理由をお互いに説明してみる
このような取り組みは、単なる資産形成にとどまらず、夫婦の信頼関係そのものを深める土台となっていくでしょう。
第4章:「いざというとき」も安心なリスク管理術
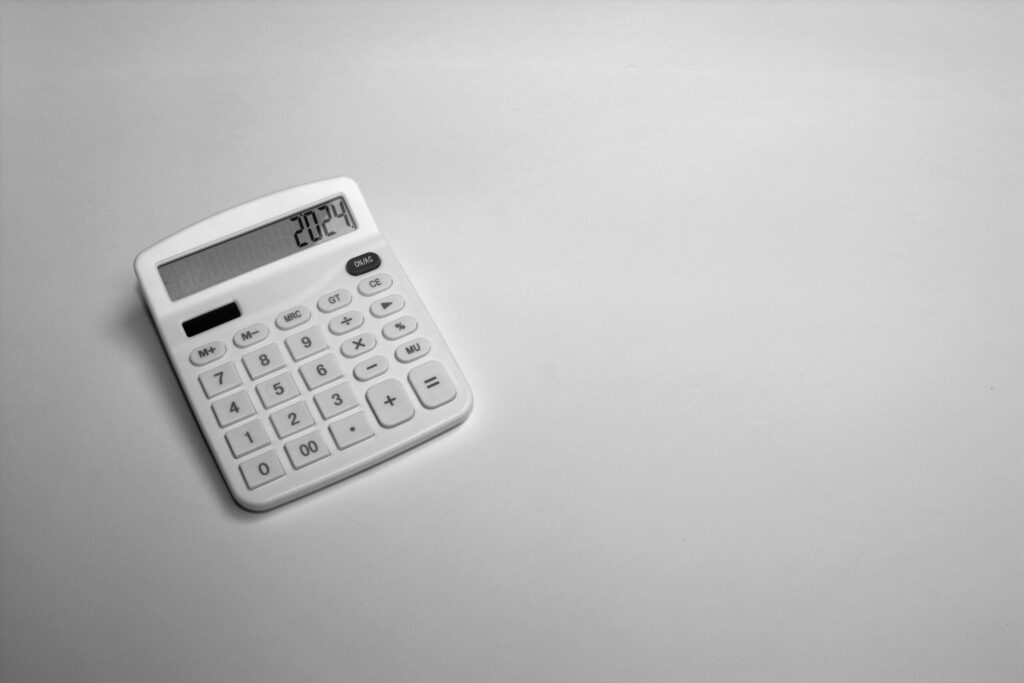
保険は“保険屋さんの言うがまま”ではNG
結婚を機に保険に入る、あるいは見直すという人は多いですが、「とりあえず提案された内容で契約した」「なんとなく不安だから加入した」というケースも少なくありません。
しかし、これは非常に危険な思考です。なぜなら、**保険は“安心”を買う代わりに“固定費”という形で家計を圧迫する可能性がある”**からです。
保険を資産形成の観点から見直すには、まず以下の2点を意識しましょう:
- 本当に必要な補償内容か?
- コストパフォーマンスは適切か?
医療保険においては、すでに健康保険制度が高額療養費制度を備えているため、全額自己負担になるリスクは限定的です。また、生命保険も、子どもがいない段階では必要性が低い場合が多いのが実情です。
言い換えるなら、「とにかく全部入る」ではなく、“必要最小限”かつ“費用対効果の高い保険”に絞るべきということです。
医療・死亡・所得補償保険の本質的な見直し方法
以下は、代表的な保険とその必要性を夫婦のライフステージに応じて整理したものです。
| 保険種別 | 概要 | 新婚夫婦における必要性の目安 |
|---|---|---|
| 医療保険 | 入院・手術などに対応 | 高額療養費制度があるため、最低限でOK |
| 生命保険 | 配偶者・子どもへの死亡保障 | 子どもがいない場合は原則不要〜低額 |
| 所得補償保険 | 働けなくなったときの補償 | 共働き家庭では要検討(メイン収入が片方に集中している場合は重要) |
特に注意したいのが、“見えない固定費”になっている高額な終身保険や特約付き保険。
これらは一見すると「貯蓄性があるからお得」と思われがちですが、実は運用効率が非常に低いものも多く存在します。
保険で資産形成をするのではなく、「資産形成は投資で、リスクヘッジは保険で」と役割を明確に分けることが、将来的な資産の最適化につながります。
投資と保険の“すみ分け”が老後資産を左右する
長期的な資産形成を目指すうえで、投資と保険は“バランス”が鍵を握ります。
どちらかに偏ると、以下のようなリスクが発生します:
- 保険に偏ると? → 毎月の保険料が重くなり、貯蓄や投資の余力がなくなる。運用効率も悪く、将来的な資産形成が遅れる。
- 投資に偏ると? → 万が一の病気・事故でまとまった出費が発生したとき、資産を取り崩す羽目になる。
たとえば、30代夫婦がそれぞれ月1万円ずつ保険に加入していれば、年間24万円が“固定費”として消えていきます。その24万円を「つみたてNISA」に充てた場合、20年後には約800万円近い資産に成長する可能性もあります(年利5%想定)。
もちろん、“保険=不要”という話ではありません。
大切なのは、「どこまでを保険に任せ、どこからを自己資金でカバーするか」という自己防衛ラインの設計です。
この“すみ分け”ができるかどうかで、老後の資産状況やライフスタイルに大きな差がつくと言っても過言ではありません。
補足:保険の見直しは「プロの第三者」に相談するのがベスト
最後にアドバイスを一つ。保険の見直しを行う際は、保険販売を主目的としない独立系FP(ファイナンシャルプランナー)や、乗合代理店でのセカンドオピニオンを活用することをおすすめします。
というのも、特定の保険会社に属する営業担当者の場合、どうしても「売りたい商品に誘導される」リスクがあるためです。
- 相談料が発生しても、中立な立場からアドバイスしてくれる専門家
- ライフプラン・収支・保有資産に応じた“本当に必要な保障”だけを提案してくれる人
このようなプロと相談することで、感情や広告に流されることなく、合理的なリスク管理設計が可能になります。
第5章:住宅購入は「夢」ではなく「資産戦略」
賃貸 vs 持ち家は“ライフプランと金利次第”
「そろそろマイホームを……」。
新婚生活が落ち着き、将来の家族計画が見えてくると、住宅購入を検討する方は少なくありません。しかし、「持ち家=正解」「賃貸=損」といった単純な公式は、もはや成り立ちません。
実際には、ライフスタイル、転勤リスク、金利環境、子どもの教育方針など、複数の要素が絡み合い、「どちらが得か?」は人によって大きく異なります。
賃貸のメリットは、「柔軟性の高さ」と「修繕・固定資産税などのコストが不要な点」。一方、持ち家は「資産としての蓄積(売却・賃貸可能性)」や「長期的な住居費の安定性」が魅力です。
ポイントは、“住まい”を「コスト」としてだけでなく、「資産」にもなりうる存在として捉える視点。つまり、「住宅=生活の舞台」+「金融資産のひとつ」という2つの顔を持つのです。
固定金利と変動金利の選び方(2024年以降の金利動向も踏まえて解説)
住宅ローンを組む際、多くの人が悩むのが「固定金利」か「変動金利」かの選択です。
それぞれにメリット・デメリットがあるため、家庭の状況や将来の金利見通しを踏まえた“戦略的選択”が求められます。
| 金利タイプ | 特徴 | 向いている世帯 |
|---|---|---|
| 変動金利 | 当初は金利が低く、毎月の返済額も抑えられる。将来的に金利上昇リスクあり | 貯蓄に余裕があり、短期集中で返済する予定がある家庭 |
| 固定金利 | 金利が高めだが、返済額が一定で計画が立てやすい。金利上昇の影響を受けない | 安定志向で、長期ローンを前提とする家庭 |
2024年現在、日本銀行の金融政策により超低金利状態は徐々に緩和傾向にあります。変動金利の魅力は依然大きいものの、今後の金利上昇リスクを無視できない局面に差し掛かっていることは確かです。
特に、「子どもが生まれる」「教育費が増える」「片働きになる可能性がある」といった家庭は、返済額の変動が家計に与えるインパクトが大きくなるため、固定金利を検討する価値があります。
頭金・諸費用・団信のリスクを数値で把握するチェックポイント
住宅購入では、「価格」ばかりに目が行きがちですが、実際には頭金や諸費用、保険、維持コストなどを含めた“総合的な資金計画”が必要です。
✅ 頭金の目安
- 物件価格の10〜20%程度が一般的
- 例:5,000万円の物件 → 500〜1,000万円の頭金
✅ 諸費用の内訳
- 仲介手数料、登記費用、火災保険、印紙税など
- 物件価格の6〜8%前後を見込むのが一般的
✅ 団信(団体信用生命保険)の重要性
- 住宅ローン契約者が死亡または高度障害になった場合、残債がゼロになるという生命保険の役割も果たす
- 最近では「がん・三大疾病付き団信」なども増加(保険料上乗せあり)
また、マンションであれば管理費・修繕積立金が毎月発生し、戸建てであれば10〜15年後に外壁・屋根の大規模修繕費が必要になるケースも。
こうした“見えないコスト”まで踏まえて、無理のない資金計画を立てることが、住宅を「夢のマイホーム」ではなく「堅実な資産」として位置づける第一歩となります。
補足:持ち家は“資産”になるか?出口戦略も視野に
「家を買ったら一生住む」ではなく、近年では出口戦略(売却・賃貸)を意識した住宅購入が注目されています。
- 将来売却しやすいエリアか?
- 資産価値の落ちにくい物件か?
- 老後にリバースモーゲージ(自宅を担保に生活費を借りる制度)を活用できるか?
このような視点で物件を選ぶことで、将来的に「住まいが資産を支える」状況をつくることができます。
つまり、“今の暮らし”だけでなく、“将来の選択肢”を広げるために住宅をどう扱うか。それが、資産形成における住宅戦略の核心なのです。
第6章:節税しながら資産形成する夫婦が増えている理由
新NISA制度(2024年〜)で年間360万円まで非課税投資が可能に
かつては年間40万円(つみたてNISA)または120万円(一般NISA)という上限がありましたが、2024年の制度改正により、NISAは大きく生まれ変わりました。
これにより、投資による資産形成における“節税インパクト”が飛躍的に向上しています。
✅ 新NISAの概要(2024年改正後)
| 区分 | 年間投資枠 | 生涯投資枠 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 成長投資枠 | 240万円/年 | 最大1,200万円 | 株・アクティブ型投資信託も対象 |
| つみたて投資枠 | 120万円/年 | 最大600万円 | インデックス投資信託など対象 |
夫婦で活用すれば、年間最大720万円、非課税枠合計で最大3,600万円の運用が可能。
仮に年利5%で20年運用できたとすれば、税引前で約6,000万円以上の資産が見込まれます(※単利・複利計算条件による)。
通常、株や投信の利益には約20.315%の税金がかかりますが、NISAなら非課税。
この“差額”が長期的には数百万円単位になるため、最強の節税投資制度と言われる理由も納得です。
iDeCoと住宅ローン減税の併用で“税制優遇の最大化”
iDeCo(個人型確定拠出年金)も、節税という観点から非常に優れた制度です。
こちらも新NISAと並行して活用することで、より強固な資産形成と税金対策が可能になります。
✅ iDeCoの3つの節税ポイント
- 掛金が全額所得控除(課税所得が減る → 所得税・住民税も減る)
- 運用益も非課税
- 受取時も控除がある(退職所得控除 or 公的年金控除)
たとえば、年収600万円の会社員が月23,000円をiDeCoに拠出した場合、年間で約5.5〜6万円程度の節税効果が見込めます(所得税+住民税)。
さらに、住宅ローン控除も併用可能です。
特に住宅購入初年度は「住宅ローン減税」+「iDeCo」+「NISA」で、年10万円以上の節税が実現できるケースも珍しくありません。
これらの制度は、複雑に見えても“一度仕組み化すれば”自動的に恩恵を受け続けられる点が魅力です。
所得分散・扶養調整・贈与の基本的考え方も解説
新婚夫婦であっても、税の知識は“知っているかどうか”だけで差が出る領域です。特に以下の3つは、夫婦の収入構成や将来の相続を考える上で押さえておくべき重要ポイントです。
✅ 所得分散
夫婦で収入が偏っている場合、「高所得者に課税が集中しやすい」という税制の性質を利用して、収入や資産を分散させることが節税につながります。
- 個人事業主やフリーランスであれば、配偶者に仕事を手伝ってもらい「配偶者への給与支払い」で所得分散
- 不動産や株式投資の名義を分けることで、課税所得を夫婦で分散
✅ 扶養調整
配偶者控除や配偶者特別控除は、配偶者の所得が一定額以下である場合に利用可能です。
たとえば、配偶者の年収が103万円以下なら、最大38万円の控除が適用されます(2025年現在の制度)。
この「103万円の壁」や「150万円の壁」などの境界を把握し、収入調整を行うことで、世帯全体での税負担を最適化できます。
✅ 贈与の活用(110万円の非課税枠)
年間110万円までは、贈与税がかからずに資産移転が可能です。
これは「夫婦間の資産調整」「子どもへの教育資金移転」などに活用されることが多く、将来的な相続税対策にもつながります。
たとえば、10年間連続で贈与すれば、1,100万円分の資産移転が非課税で完了します。
家計を“家族全体で捉える”視点が、こうした制度を最大限に活かす鍵となるでしょう。
ワンポイント:税制活用の“初期設計”が、将来の安心につながる
節税制度というのは、「知っている人だけが得をする」非常に不公平な世界でもあります。
ですが、逆に言えば——今この瞬間から情報を得て、行動に移せば、誰でもその恩恵を受けることができるのです。
- NISAやiDeCoの口座を開設する
- 扶養や控除を意識して収入設計する
- 贈与・相続について早めに話し合う
こうした「ちょっとした行動」が、10年後、20年後の家計に数百万円単位の影響を与えることもあります。
投資も税金も、「スタートが早いほど有利」。
だからこそ、新婚期はその“設計”を始める絶好のタイミングなのです。
第7章:「子ども」「老後」「キャリア変化」ライフイベントごとの資金戦略
出産・育休:教育費の準備と“出費増”への対策
子どもの誕生は、人生の中でもっとも喜ばしいイベントの一つであると同時に、“支出が急増するタイミング”でもあります。
厚生労働省の統計によると、出産費用は平均で約50万円前後(健康保険の出産育児一時金で実質負担は軽減されますが、私立病院や個室希望などで超過も)。
さらに育児休業中は、所得が減少するケースも多く、共働き家庭であっても一時的に家計が圧迫される状況が発生します。
そこで重要になるのが、“出産前からの備え”と“出費構造の見直し”。
対策ポイント
- 出産・育児用品にかかる初期コストを見積もり、専用の積立口座を設ける
- 出産費用の一部を出産育児一時金(原則50万円)で補填できるよう、医療機関と事前確認
- 育休中の収入減に備えて、3〜6ヶ月分の生活費を緊急資金として確保
また、出産後すぐに始めておきたいのが「教育費」の積立です。
教育費は“年齢別・段階別”に分けて準備する
文部科学省のデータによると、子ども一人を大学まで育てるのに必要な教育費は、公立ベースでも約1,000万円前後、私立を含めると2,000万円以上とも言われています。
漠然とした金額に圧倒されそうになりますが、実際には段階的な支出になります:
| 教育段階 | 年間費用(公立) | 年間費用(私立) |
|---|---|---|
| 幼稚園〜高校 | 約50〜100万円 | 約100〜150万円 |
| 大学 | 約100万円(国公立) | 約150〜200万円(私立) |
こうした支出に備えて、以下のような制度を活用するのが効果的です:
- ジュニアNISA(2023年で新規口座受付終了) → 2024年以降は新NISAで代用
- 学資保険ではなく、つみたて投信で“柔軟性と利回り”を優先
- 子どもの誕生日ごとに積立額やポートフォリオの見直しを行う
未来のためのお金を“ただ貯める”のではなく、“増やしながら貯める”発想が鍵になります。
住宅ローン返済中の転職や独立にどう備える?
ライフイベントとして意外と多いのが、「キャリアの転換期」。
転職、キャリアアップ、副業、起業……。30代〜40代は、こうした動きが活発化する時期でもあります。
しかし、ここで見落としがちなのが、住宅ローンとの関係性。
住宅ローンとキャリア変化のリスク
- 転職直後は住宅ローン審査が通りにくくなる(特に勤続年数が短い場合)
- 独立後すぐは不安定な収入が続き、返済の余裕がなくなる可能性
- 健康状態によって団信の加入・継続が難しくなるケースもある
そのため、以下のような備えが有効です:
- 転職・起業前に生活防衛資金として6〜12ヶ月分の支出を確保
- 団信・収入補償保険などの“返済サポート体制”を事前に整える
- ローン残高や返済比率(年収の25〜30%以内)を常に見直し、柔軟に繰上返済も検討
また、転職や独立に際しては、iDeCoや企業型DCなどの年金資産の取り扱いにも注意が必要です。
制度の継続・移管を怠ると、長期的な老後資金形成に支障が出る可能性があります。
老後資金2,000万円問題への現実的アプローチ
「年金だけでは老後資金が足りない」——いわゆる「老後2,000万円問題」が話題になったのは2019年ですが、それ以降も物価上昇や年金支給開始年齢の延長など、不安要素は増す一方です。
新婚夫婦にとって老後はまだ遠い未来かもしれませんが、“今から積み立てること”こそが最大の保険になります。
老後資金形成の具体的ステップ
- 生活費×30年分×インフレ率=目標額を見積もる
- iDeCo・企業型DC・新NISAで“税優遇+長期運用”を最大活用
- 公的年金の受取額を試算(ねんきんネット)し、不足分を逆算
仮に毎月3万円を年利4%で30年間積み立てた場合、最終的な資産は約1,700万円になります(複利効果による)。
このように、“今できることを今から始める”ことで、未来に対する漠然とした不安を“具体的な数字”でコントロールできるようになります。
第8章:「やってはいけない」夫婦資産運用の落とし穴
利回りだけを追う危険な投資の罠
資産形成を意識し始めると、ついつい「どれだけ増やせるか」「どの投資商品が一番儲かるか」にばかり目が向いてしまいがちです。
しかし、利回りだけを追いかけることは、最も典型的かつ危険なミスのひとつ。
以下のような商品には注意が必要です:
- 高配当をうたう新興国通貨建て債券
- 元本保証を“ほのめかす”ような不動産クラウドファンディング
- SNSやYouTubeで話題になった「流行りもの投資」(例:仮想通貨・個別株の一点買い)
これらはたとえ“表面的な利回り”が魅力的に見えても、リスクの高さ・情報の不透明性・元本割れリスクといった代償が潜んでいます。
資産運用における基本は、「リスクとリターンはセット」。
“5%以上の利回り”を期待するなら、それに見合ったリスクがあることを理解し、夫婦で納得の上で意思決定することが不可欠です。
保険・住宅・教育…感情で決めると失敗する
資産形成においては、“感情が判断を曇らせる”ことがしばしばあります。
- 「家は子どもができる前に買わなきゃ」
- 「保険に入っていれば安心だし、親もそうしてた」
- 「子どもの教育にはいくらでも出してあげたい」
これらの考え方自体は自然なものですが、資産の全体設計を無視して感情だけで決めると、家計が破綻する可能性があるのです。
たとえば、将来の収入減や退職後の生活費を無視して住宅ローンを組んだり、学費にすべてを投じた結果、自分たちの老後資金が枯渇してしまったりといった事例は少なくありません。
重要なのは、**感情に動かされる前に、「数字で判断する習慣」**を身につけること。
- 家の購入は「返済比率」と「資産価値」で冷静に判断
- 保険は「保障内容と費用対効果」で選定
- 教育費は「上限を決め、必要に応じて奨学金や制度を活用」
“感情に寄り添いながらも、数値で方向性を決める”。
このバランス感覚こそが、夫婦資産運用を成功に導く鍵となります。
知らないと損する「夫婦名義」や「相続・贈与」の基本
結婚生活を送る中で、意外と見落とされがちなのが「名義」に関する話題です。
これは、将来的な税務リスクや相続トラブルに直結する重要なテーマでもあります。
✅ 住宅ローンや資産の名義が偏っていると…
- 住宅ローン控除が一方の配偶者にしか適用されない
- 将来売却時、譲渡所得税の負担が一人に偏る
- 相続時、贈与扱いになるリスク(夫の資金で妻名義にした場合など)
✅ 贈与に関する誤解も多い
「夫婦だから、お金を渡しても贈与にならない」は誤解です。
実際には、夫婦間であっても年間110万円を超える贈与には課税リスクがあります(例外的に、婚姻期間が20年以上の配偶者に対する居住用不動産贈与は2,000万円まで非課税)。
また、教育資金の一括贈与なども非課税制度がありますが、制度ごとに厳格な条件があるため、税理士や専門家に相談の上で進めることが望ましいでしょう。
ワンポイント:夫婦間で“お金の責任分担”を曖昧にしない
意外と多い落とし穴が、「どちらが何を支払うかが曖昧なまま数年経ってしまう」パターンです。
これにより、
- 無駄な支出が重複していた
- 実際にどちらがどれだけ負担していたかが不透明
- 離婚・相続時に“揉める原因”になりかねない
といったトラブルに発展することも。
新婚期にこそ、「支出・貯蓄・投資の分担と記録の習慣」を夫婦で共有しておくことが、“お金に関する信頼関係”を築く大前提となります。
第9章:新婚1年目からやるべき資産形成アクション10選
「知っていること」と「やっていること」は、資産形成において天と地ほどの差を生みます。
この章では、今日から始められる10の具体的なアクションをリストアップしました。
どれも難しくありませんが、“実行すれば将来の資産と安心感に直結”するものばかりです。
1. 家計の共有化と月次会議の開催
- 収支を“夫婦の共同責任”として可視化
- 毎月1回、「家計ミーティング」を開いて家計簿・目標・支出振り返りを共有
これだけで、「知らないうちにお金が減っていた」「なんとなく貯まらない」状態を防げます。
2. 家族信託・遺言の基礎を学ぶ
- 将来の相続や認知症リスクに備え、“財産の管理者”を事前に定める制度
- 早すぎることはありません。40代以降は準備のスタート期と考えて◎
専門家の無料セミナーや書籍などから、まずは仕組みを学ぶだけでも大きな前進です。
3. 投資本を夫婦で1冊読む
- 「お金の話」は感覚ではなく、“共通の知識”から始めるのがベスト
- おすすめは『お金の大学(両学長)』『本当の自由を手に入れる お金の教室』など
読み終えたら、感想を話し合って投資方針をすり合わせてみましょう。
4. 新NISA口座の開設と商品選定
- 2024年以降の新NISA制度を最大限に活用するため、夫婦で年間720万円まで非課税運用が可能
- まずは証券口座開設→投資信託の積立設定までを1セットで
「eMAXIS Slim全世界株式」などからスタートすれば、迷わず実行できます。
5. iDeCoを活用し税負担を軽減
- 老後資金を“節税しながら育てる”手段として、iDeCoは非常に優秀
- 会社員でも月23,000円まで掛金可能。所得控除により、年間5〜6万円の節税効果も
開始が早ければ早いほど、複利効果の恩恵も大きくなります。
6. 支出カテゴリ別に無駄を洗い出す
- 例えば「サブスク」「コンビニ」「外食」「スマホ料金」などを1ヶ月間だけ詳細記録
- 不要な固定費・習慣的支出を見つけて月5,000円削減できれば、年間6万円の節約に
節約とは我慢ではなく、“気づき”です。
7. 保険の見直しを専門家に依頼
- 加入済みの保険が本当に必要か、過剰保障かをチェック
- 独立系FPや乗合代理店など、販売ではなく“診断”を目的とした相談先を選ぶのがコツ
高額な終身保険・貯蓄型保険の見直しだけで、毎月1万円以上のコスト削減につながることも。
8. 教育資金準備をジュニアNISA/新NISAで開始
- ジュニアNISAは新規受付終了のため、新NISAでの積立投資が有効
- 子ども1人あたり「月1万円×18年」で、教育資金として約400万円以上を準備可能(年利3〜5%想定)
“学資保険だけ”では足りない時代に、新NISAは心強い味方です。
9. キャリア設計と住宅取得時期の検討
- 住宅ローンは「金利」「年齢」「転職の有無」などに大きく左右される
- 賃貸と購入の比較、転職後の融資条件、夫婦の名義・借入条件などをシミュレーション
不動産選びは“感情”ではなく“人生設計”から逆算して考えるべきです。
10. 夫婦の資産運用計画を年1回アップデート
- 1年ごとに「運用成績」「目標の達成度」「生活環境の変化」を振り返る
- 運用方針や積立金額の微調整、ポートフォリオの再構築などを行う
「年末の夫婦資産会議」を習慣にしておくと、未来が見えるようになります。
これらのアクションを1つずつでも取り入れていけば、新婚1年目から将来の“経済的不安”を着実に遠ざけることができます。
資産形成は、派手なことをする必要はありません。コツコツ、淡々と、でも確実に。
そしてそれを、信頼できるパートナーと一緒に楽しみながら進めていくことこそが、人生をより豊かにしてくれるのです。
まとめ:人生のパートナーと、お金のパートナーになるということ

結婚とは、「人生を共に歩むこと」を約束する営みです。
しかし、それは単に一緒に暮らすという意味にとどまらず、「将来への責任を共有する」という覚悟でもあります。
その責任の中でも、お金——つまり**“人生を支える土台”としての資産形成**は、見過ごせないテーマです。
資産形成は、ふたりの“生き方”を映す鏡
このガイドを通じて見てきたように、資産形成とは単に「お金を貯める」「投資で増やす」ことではありません。
それは、夫婦がどんな未来を望み、どんな価値観を持ち、どんな人生を設計するか——そうした生き方の反映なのです。
- ふたりでお金について話し合うこと
- お互いの価値観を知り、妥協点を探ること
- 目先の損得ではなく、“長期の幸福”を最優先にすること
資産形成のプロセスそのものが、夫婦の信頼関係を育み、未来への安心感を築く時間でもあるのです。
小さな一歩が、大きな未来を変えていく
「投資は難しそう」「まだ早いかも」「貯金すらちゃんとできてない」——そんな声が聞こえてきそうですが、大丈夫です。
誰もが最初は初心者。大切なのは、“知識”ではなく“行動”です。
このガイドで紹介したステップのうち、たったひとつでもいい。今日から始めてみること。
それが、10年後、20年後、ふたりの生活を確実に変えるきっかけになります。
未来は「準備する人」に微笑む
不確実な時代だからこそ、希望を持てる備えが必要です。
そしてそれは、収入の多寡ではなく、「知り、選び、動く」ことから始まります。
- 制度を理解し、適切に活用する
- 浪費を減らし、意志ある支出を心がける
- パートナーとともに“資産”という人生の支柱を築いていく
そのすべてが、「未来の自分たち」を守る最強の防御であり、最高の攻めになります。
ふたりの未来は、ふたりで育てるもの
最後にお伝えしたいのは、お金の話は、愛の延長線上にあるということです。
本気で向き合うことで、夫婦の絆が深まり、人生設計にリアルな輪郭が生まれます。
“資産形成”は、未来の夢に輪郭を与え、日々の暮らしに芯を与える力。
ふたりで歩む人生の中で、それは決して冷たい数字の話ではなく、**あたたかな暮らしを紡ぐための“手段”**であることを、どうか忘れないでください。
今日が、ふたりの資産形成のはじまりの日になりますように。

ファイナンス専門ライター / FP
資産運用、節税、保険、財産分与など、お金に関する幅広いテーマを扱うファイナンス専門ライター。
金融機関での勤務経験を活かし、個人投資家や経営者向けに分かりやすく実践的な情報を発信。特に、税制改正や金融商品の最新トレンドを的確に捉え、読者の資産形成に貢献することを得意とする。





