ここ数年、ビットコインやイーサリアムなどの暗号資産(クリプトアセット)は、ただの投機対象ではなく、資産保全や分散投資の手段としても注目されるようになりました。特に2020年以降の世界的な金融緩和を背景に、富裕層による暗号資産の保有比率は増加傾向にあります。
そして今、新たな問題として浮上しているのが「贈与」──すなわち、資産を家族に引き継ぐという行為です。価格が急騰した資産を、税負担を最小限に抑えて次世代へ引き渡すにはどうしたらいいのか。このテーマは、もはや一部の富裕層だけでなく、準富裕層にとっても喫緊の課題と言えるでしょう。
「現金で渡す」時代から「クリプトで引き継ぐ」時代へ
従来の資産承継では、現金、不動産、有価証券が中心でした。しかし、ブロックチェーン上で記録される暗号資産は、保有の匿名性・グローバルな移動性・分割性などに優れており、「引き継ぎやすさ」という点でも注目を集めています。
とはいえ、暗号資産には税務上のグレーゾーンや注意点が多く存在します。「ただウォレットを共有すれば贈与にならないのでは?」という誤解から始まり、「相場変動をどう評価するか?」という実務的な問題まで、想定すべきリスクは少なくありません。
本稿では、富裕層が暗号資産を贈与する際に押さえておくべき法制度、税務実務、リスクとその対処法までを包括的に解説します。
第1章:暗号資産と贈与税の基本構造

贈与とは何か?どこからが課税対象になるのか
税務上の「贈与」とは、個人が他の個人に対し、無償で財産を移転することをいいます。つまり、対価を受け取らずに財産を渡せば、それが暗号資産であれ現金であれ、「贈与税」の対象になり得るのです。
日本の贈与税は「受贈者」──つまり財産を受け取った側に課税される仕組みです。これは相続税とは異なるポイントであり、贈与者側は非課税である反面、受け取る側の税負担が非常に重くなる場合もあります。
贈与税の課税基準と税率(基礎控除・累進課税)
贈与税の課税対象は、「1月1日から12月31日までの1年間に受け取った贈与財産の合計額」に基づいて判断されます。そして、年間110万円までの贈与には「基礎控除」が適用されるため、それ以下であれば申告・納税の必要はありません。
しかし、110万円を超えた部分については最大55%という高率の累進課税が適用されるため、数百万円以上の暗号資産を一括で贈与する場合は、慎重な設計が必要となります。
「評価額」はどの時点?暗号資産特有の算出方法
暗号資産の贈与において最も難しいのが、「評価額の算定時点」です。国税庁は、暗号資産の贈与においては「贈与が成立した日の時価(交換所での価格)」を基準とするよう定めています。
たとえば、ある日ビットコインを子どもに贈与した場合、その日の終値や取引価格を基準に評価し、その額に基づいて贈与税を計算する必要があります。仮に、その後価格が暴落しても、それは贈与税には影響しません。
つまり、評価のタイミングが悪ければ、「税だけが高く、資産価値は目減りしている」という不本意な状況も起こり得るのです。
第2章:暗号資産を贈与する際の実務的な注意点

取引記録の保存義務と贈与の証明方法
贈与は「事実の証明」ができなければ、税務署に否認されることがあります。特に暗号資産の場合、「いつ、どのアドレスから、どのアドレスに、どの数量が、どんな意図で移されたか?」を明確に記録することが重要です。
そのためには、以下のような情報を整理・保存しておく必要があります:
- トランザクションの記録(ブロックチェーン上の履歴)
- 贈与契約書(贈与の意思表示を文書化)
- 贈与者・受贈者のウォレットアドレスの関連性を示す資料
税務調査が入った際に、これらが「贈与だった」と客観的に証明できる資料になります。
贈与の事実を示す書面・契約書の作成例
形式は自由ですが、贈与契約書を作成することで、贈与の成立を明確に示すことができます。内容としては、以下の項目を盛り込むのが望ましいです:
- 贈与日と契約締結日
- 贈与者・受贈者の氏名と住所
- 贈与する暗号資産の種類、数量、評価額
- 贈与に関する意思表示の記載(無償であることなど)
これに加えて、双方が署名・捺印することで、贈与の事実が形式的に成立しやすくなります。
子や孫への贈与は「学費」や「生活費」として非課税にできる?
贈与税の例外として、「生活費」「教育費」などの目的で支出される場合、贈与とみなされず非課税になるケースがあります。ただしこれは、「その都度、必要な都度」に限られ、まとめて多額を渡すと課税対象になる恐れがあります。
たとえば、孫の大学入学費用を支払う目的で暗号資産を贈与する場合、そのタイミングと支出の具体性が問われます。現金化せずウォレットでの保管状態では、単なる資産移転とみなされる可能性が高く、事前に税理士と相談しておくことが肝心です。
第3章:富裕層が直面する贈与リスクと税務調査の盲点
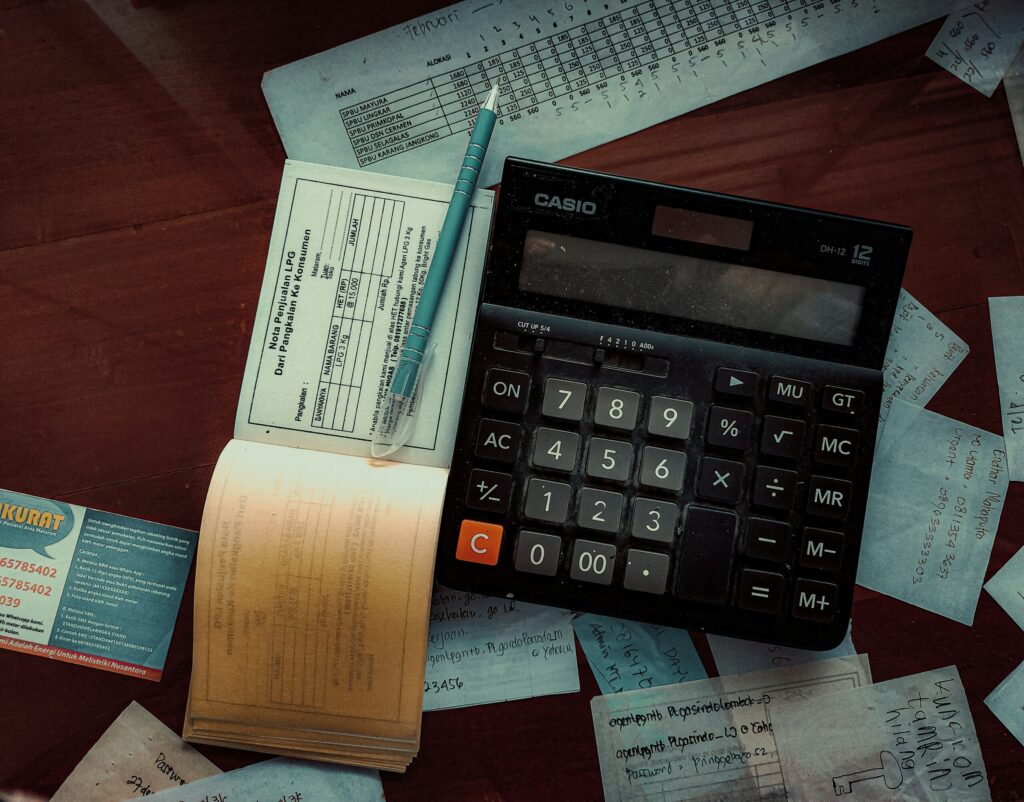
高額な贈与による調査リスク
富裕層にとっては、資産の一部を家族や子どもに贈与することは決して珍しい話ではありません。特に暗号資産のように、将来性があり、流動性にも優れる資産であれば、積極的に“次世代へ引き継ぐ”手段として検討されることもあるでしょう。
しかし、ここで注意したいのが「税務署による調査のリスク」です。
贈与税は自己申告制です。つまり、受贈者が自ら贈与を受けた事実を申告しなければならないわけですが、富裕層が高額な資産を移動させると、その情報は「名寄せ」によって税務署に把握される可能性があります。たとえば以下のようなきっかけから調査が入ることがあります:
- 大学入学に伴い突如として多額の納税が始まった未成年
- 複数年にわたる所得不一致
- 海外資産や暗号資産に関する国際的な情報共有(CRSなど)
特に、暗号資産は金融機関を介さずに送金できるため、資産移動が把握しにくいと考えられがちですが、取引所のKYC強化やCRSの適用範囲拡大により、監視の目は年々厳しくなっています。
仮想通貨の送付と贈与の認定の違い
「仮想通貨をウォレットからウォレットに送っただけだから贈与ではない」──そんな考え方が、税務署に通じるでしょうか?
結論からいえば、通じません。
贈与は“無償で財産が移転された事実”に基づいて判断されるため、形式がどうあれ、贈与者の資産が減り、受贈者の資産が増えたならば、そこには贈与があったとみなされる可能性が高いのです。
そのため、贈与税の申告を回避しようとして、「貸した」「保管しているだけ」という説明で逃げ切ろうとする例も見られますが、税務調査では「その資産を自由に使えるのかどうか」という実質面が問われます。ウォレットの秘密鍵を渡した時点で、事実上の“支配権”が移っていると判断されるケースもあります。
暗号資産の「隠れた贈与」が発覚するケースとは
近年、暗号資産の贈与が発覚するパターンで増えているのが、「所得税や消費支出との不一致」による調査です。たとえば、次のような例があります。
- 収入が少ないのに高額な車を購入した未成年
- 海外取引所にある暗号資産を、日本円に換金した記録が急に増えた個人
- フリーランスの子どもが、親のウォレットから定期的に資金移動を受けている
これらはすべて、暗号資産を利用した“見えにくい贈与”として、税務署にチェックされやすい事例です。特に2022年以降は、金融庁と連携した暗号資産取引所の情報開示が進み、取引所に登録されたKYC情報(氏名・住所・取引履歴)が直接調査の材料として使われるようになっています。
また、税務署は「現金に換金された後」に注目することが多いため、「ウォレット上にあるうちは見つからないだろう」という考えは非常に危険です。
第4章:贈与税対策の実践戦略
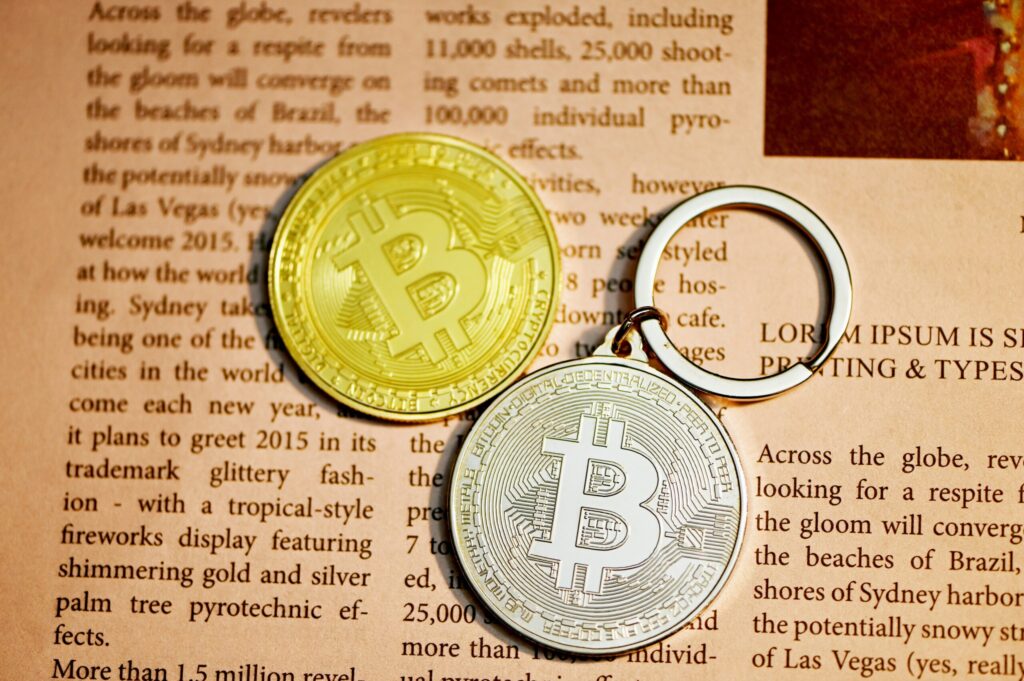
年間110万円の非課税枠の使い方と分割贈与
贈与税対策の第一歩として、誰もが利用できるのが「年間110万円の基礎控除」です。これは、受贈者1人あたり、1年間に110万円までの贈与は非課税になるという制度で、暗号資産の贈与にも当然適用されます。
たとえば、暗号資産を110万円相当で毎年少しずつ子どもに贈与する「分割贈与戦略」を取ることで、大きな贈与税を回避することが可能です。贈与税は「1月1日〜12月31日」の暦年で計算されるため、年末年始をまたいで贈与を分割することで、税務上の負担を軽減できます。
ただし、同一人物に毎年同じタイミングで110万円相当を贈与すると、「定期贈与(連年贈与)」とみなされるリスクもあるため、金額やタイミング、贈与形式に変化をつける工夫が求められます。
家族信託・民事信託を活用したスマートな移転スキーム
もう一歩進んだ戦略として、近年注目されているのが「家族信託(民事信託)」を活用した贈与です。信託とは、財産の管理・運用を第三者(または家族)に任せる仕組みで、財産の所有権と管理権を分けて設計できるのが大きな特徴です。
たとえば、以下のような設計が可能です:
- ビットコインなどを父親が「委託者」として信託に出す
- 子どもを「受託者」として管理を任せる
- 利益を得る「受益者」も別に設定する(例:孫)
この仕組みによって、形式上は贈与ではなく「信託の設計による管理移転」となるため、贈与税や相続税のタイミングをコントロールすることができます。
もちろん、この方法には高度な法的知識が必要となるため、必ず税理士・弁護士とチームで設計することが前提です。
「法人を使う」は節税か脱税か?グレーゾーンの見極め方
暗号資産の税務戦略として、「法人を設立してそこで保有・贈与を行う」スキームが話題になることがあります。法人税率は個人よりも低く、一定の節税効果が見込まれるのは事実です。
しかし、ここには大きな“グレーゾーン”が存在します。たとえば、
- 実態のないペーパーカンパニーを作って暗号資産を保有させる
- 贈与目的で法人を利用しながら、管理実態は個人にある
- 法人と家族間の取引価格が不自然に安い
これらはすべて、税務署から「租税回避行為」として否認される可能性があります。節税と脱税の境界は非常に曖昧であり、「実態があるかどうか」「経済合理性があるかどうか」が判断基準となります。
そのため、「法人を活用して贈与税対策を行いたい」と考える場合は、必ずプロの目を通し、「形式と実質の整合性」を確保することが必要です。
第5章:相続との違いから考える最適な引き継ぎ方法

相続税と贈与税の比較:どちらが得か?
資産の引き継ぎにおいて、多くの方が悩むのが「相続と贈与、どちらが税制上有利なのか?」という問いです。
結論から言えば、「一概には言えない」が答えです。なぜなら、相続税と贈与税では課税体系や控除額、税率が異なるため、ケースバイケースでの検討が必要となるからです。
まず、贈与税は年間110万円の基礎控除がある一方で、税率は最高55%と非常に高い。一方、相続税は3,000万円+600万円×法定相続人の数という基礎控除が大きく、税率も一定額以下であれば抑えられる可能性があります。
ただし、相続の場合は「いつ亡くなるか分からない」ことと、「評価時点での資産価値」が不明なことが大きなリスク。特に暗号資産のように価格変動が激しい資産は、相続時に予想外の評価額となり、高額の相続税が課されるケースもあるのです。
贈与による資産移転のタイミング設計
暗号資産の贈与を考える際に最も重要なのが「タイミング」です。税務上は贈与が成立した日=受贈者に資産が渡った日をもって評価されるため、その時点の相場によって課税額が大きく変わります。
たとえば、ビットコインの相場が一時的に下落しているタイミングで贈与すれば、評価額を抑えることができ、結果的に贈与税を低く抑えることが可能です。もちろん、その後の値上がりを想定している場合は、長期的にみて“得”になる戦略とも言えるでしょう。
このように「贈与タイミング=評価額コントロール」という視点で計画することで、将来の税負担を抑えることができるのです。
相続時精算課税制度の活用とリスク
もう一つ、贈与と相続をつなぐ制度として注目されているのが「相続時精算課税制度」です。これは、60歳以上の親から20歳以上の子どもへ贈与する場合、2,500万円まで非課税で贈与ができるという制度です。
ただし、注意点としては以下のような点があります:
- 一度この制度を選択すると、以後の贈与すべてが対象になる
- 贈与時には非課税でも、相続時には合算されて相続税の対象になる
- 暗号資産の評価や記録管理を厳密に行う必要がある
そのため、「今は課税されたくないが、将来的には相続しても良い」といった計画を立てる場合には非常に有効ですが、「本当に節税になるか?」という視点では、慎重なシミュレーションが必要です。
第6章:暗号資産贈与の成功事例・失敗事例

成功事例:家族信託×暗号資産で安心相続
G氏(60代)は、数千万円相当の暗号資産を保有する個人投資家。自身の高齢化に伴い、「いざという時に家族がアクセスできないと困る」という懸念から、税理士と弁護士の協力のもと、家族信託を設計しました。
彼は自分を「委託者兼受益者」とし、長男を「受託者」に指定。ウォレットの秘密鍵管理や資産移動の権限を明確化したことで、贈与ではなく「管理委託」としてスムーズな引き継ぎが可能に。
さらに、贈与税や相続税の課税タイミングも戦略的に設計され、資産の目減りを最小限に抑えることができました。このように、信託を活用することで「税制の壁」と「技術的障壁」の双方をクリアした成功例といえます。
失敗事例:贈与の記録を残さず税務否認されたケース
H氏(40代)は、暗号資産の価値が上昇していた2021年に、娘へ0.5BTCを「教育費の一部」として送金。しかし、贈与契約書を作成せず、ウォレットのアドレス管理も曖昧なままだったため、後の税務調査で「贈与事実を証明できない」として否認されました。
結果的に、過少申告加算税と延滞税を含めた数百万円の納税が発生。本人に悪意はなかったものの、「形式の不備」が高くついた失敗事例です。
実例から学ぶ、失敗しないための4つの鉄則
- 贈与契約書は必ず書面で残すこと
電子契約でも可ですが、明確な日付と贈与の意思、金額・資産内容を記載しましょう。 - 贈与の記録は「暗号資産取引所」「ウォレット履歴」両面で確保
税務署は事実と実態の両方を重視します。 - 評価額の基準を明確にし、記録として保存
贈与時のレート(取引所の終値など)をエビデンスとして残すこと。 - 事前に専門家のチェックを受けること
少額でも税務顧問に確認を取ることで、後々のトラブルを防げます。
第7章:税務顧問と共に描く「家族のための贈与設計図」
贈与計画の設計と専門家の役割
暗号資産の贈与は、金額が大きくなればなるほど慎重な設計が必要です。単発で終わらせるのではなく、「数年にわたる計画」として贈与戦略を練ることで、税負担を抑えつつ、家族内での資産移転をスムーズに進めることが可能になります。
こうした計画を立てる際には、税務顧問の存在が不可欠です。顧問税理士は、以下のような役割を果たします:
- 資産の棚卸しと贈与対象の明確化
- 評価タイミングと課税額の試算
- 相続・贈与のバランス設計
- 各種控除や特例の活用方法の提案
「資産の移転をどうするか?」という問いに対して、「税金の最適化」だけでなく、「家族との関係性」や「ライフプラン」まで含めた提案ができる税理士こそ、理想のパートナーと言えるでしょう。
顧問税理士との年間スケジュール管理
贈与計画は1年単位で完結するものではありません。長期的な視点から、数年にわたる「スケジューリング」が重要です。たとえば以下のようなフレームが考えられます:
- 第1四半期:資産状況の見直しと前年分の振り返り
- 第2四半期:今年の贈与計画の立案と試算
- 第3四半期:贈与対象者の変更や評価額の調整
- 第4四半期:契約書の作成・贈与実行・記録保管
この流れを毎年継続することで、贈与の「見える化」と「トラブル回避」が同時に実現できます。
弁護士・FPとのチーム体制の構築
贈与が関わるのは税金だけではありません。家族間の信頼関係や、ライフプラン全体の整合性も考慮に入れる必要があります。そこで重要なのが、税理士だけでなく、弁護士やファイナンシャルプランナーとの連携です。
- 弁護士:家族信託・遺言・贈与契約書の法的整備
- FP:贈与後の資産運用やライフステージ設計のサポート
これらの専門家がチームとして機能すれば、贈与は単なる税金対策ではなく、「家族に対する人生設計そのもの」として機能します。
まとめと注意点

暗号資産を用いた贈与は、税務上のルールが複雑で、なおかつ変化も早い領域です。しかし、だからこそ、早めに計画を立て、信頼できる専門家と連携することで、大きなアドバンテージを得ることができます。
贈与税のリスクを知らずに行動すれば、大切な資産が「税金」として消えてしまうこともあります。逆に、制度を理解し、適切な対策を講じれば、次世代に豊かさと安心を同時に渡すことができるのです。
「資産を遺す」ことは、「想いを伝える」ことでもあります。今この瞬間から、自分と家族の未来のために、贈与という行為を戦略的に考えてみてはいかがでしょうか。

ファイナンス専門ライター / FP
資産運用、節税、保険、財産分与など、お金に関する幅広いテーマを扱うファイナンス専門ライター。
金融機関での勤務経験を活かし、個人投資家や経営者向けに分かりやすく実践的な情報を発信。特に、税制改正や金融商品の最新トレンドを的確に捉え、読者の資産形成に貢献することを得意とする。





