かつてはテクノロジー好きの一部に限られていたビットコイン。今やその存在は、世界中の投資家にとって無視できない資産クラスとなりました。特に富裕層にとって、暗号資産(クリプトアセット)は株式や不動産とは異なる動きをする「非相関資産」として、資産ポートフォリオの一角を担う存在に成長しています。
2021年のピーク時には、仮想通貨全体の時価総額が約3兆ドル(約400兆円)に達しました。国内でも、一定以上の資産を保有する個人投資家が暗号資産を検討・保有する割合は年々増加傾向にあります。中でも、税務リスクを回避しつつ、資産保全・成長を両立させたいという「防衛と攻め」を両立するニーズが高まっています。
税務リスクの増大とその背景
しかしながら、この新たな投資分野には思わぬ“地雷”が潜んでいます。それが「税務」です。
暗号資産は日本国内において、基本的に「雑所得」に区分され、最大で55%(所得税45%+住民税10%)という高率課税の対象になります。しかも、課税タイミングや計算方法は極めて煩雑。富裕層の場合、海外取引や法人活用、家族間移転なども絡むため、想定以上に高度な税務設計が求められるのです。
国税庁は2017年以降、暗号資産の税務ガイドラインを整備しつつあり、2022年には国税庁が新たなFAQを公開するなど、取締りも強化されています。今や「知らなかった」では済まされない世界。富裕層にとっては、専門家との連携が不可欠となるフェーズに入ったといえるでしょう。
第1章:富裕層と暗号資産の現状

富裕層が暗号資産に注目する理由
富裕層が暗号資産に魅力を感じる最大の理由は、「非相関資産」としての役割です。株式市場や不動産市場の動向に左右されにくいため、資産全体のリスク分散に寄与します。特に世界的なインフレ傾向や地政学リスクが高まる中で、法定通貨への信認が揺らいでいる現在、暗号資産は「デジタルゴールド」としての地位を確立しつつあります。
また、ブロックチェーン技術を活用したDeFi(分散型金融)やNFTといった新たな金融エコシステムへの関心も高く、次世代の富の創出手段として期待されているのです。
投資スタイルと保有実態の分析
富裕層の暗号資産保有スタイルは、短期トレードよりも中長期ホールドが主流です。価格の乱高下を承知の上で、将来的な値上がりを狙う戦略が一般的。また、複数の取引所に資産を分散し、ハードウェアウォレットなどを利用して自己管理するケースも多い。
実際に、2022年の日経新聞調査によれば、総資産1億円以上の個人投資家のうち約18%が暗号資産を保有しており、その中の3割以上が「今後も積極的に保有を拡大したい」と回答しています。この傾向は、今後も強まると予測されます。
第2章:暗号資産に関する税務の基礎知識

所得区分と課税方法の違い
日本の税制において、暗号資産から得られる利益は基本的に「雑所得」として扱われます。つまり、給与や年金など他の所得と合算されて総合課税されるため、所得が高い富裕層ほど税率が上がる仕組みです。
また、年間20万円を超える利益が出た場合は確定申告が必要であり、損失を翌年に繰り越すこともできません(雑所得扱いの場合)。さらに、取引所間の資産移動や他の暗号資産への交換、マイニング報酬、エアドロップなどもすべて課税対象となるため、判断に迷うポイントが多いのが実情です。
取引記録の重要性と計算方法
暗号資産の税務において最も厄介なのが、「正確な取引記録の保存と損益計算」です。取引が1件であれば問題ありませんが、年間数百回にわたる売買、異なる通貨ペア間でのトレード、海外取引所とのやり取りがある場合、その計算は極めて複雑になります。
計算方法は「移動平均法」か「総平均法」が一般的で、どちらかを選択して継続適用する必要があります。税理士が対応しきれないケースも少なくなく、暗号資産に特化した会計ソフトやツール(Cryptact、Gtaxなど)の導入が現実的な解決策となっています。
申告漏れのリスクとその影響
暗号資産に関する税務申告で最も恐れるべきは「申告漏れ」です。国税庁はここ数年、特に海外取引所やウォレットを利用した取引に注目しており、情報収集の網は年々広がっています。日税ジャーナルによると、2020年には暗号資産を含む無申告・過少申告案件の調査で、1件あたりの申告漏れ所得が平均約1500万円という高額だったと報告されています。
追徴課税に加え、延滞税や加算税が加わると、実質的な納税額は2倍以上に膨らむこともあるため、富裕層であればこそ、早期の対応と継続的な記録管理が不可欠です。
第3章:富裕層特有の税務課題

高額保有者に求められる税務ガバナンス
暗号資産を多額に保有する富裕層にとって、単なる申告の「正確さ」だけでは不十分です。求められるのは、より高次元の「税務ガバナンス」です。税務ガバナンスとは、資産の保有構造、税務リスクの洗い出し、節税策の妥当性などを包括的に管理・設計する枠組みのこと。これを怠ると、税務調査の際に「意図的な隠蔽」とみなされ、重加算税や刑事告発のリスクが高まります。
特に、複数のウォレットや取引所を利用し、事業所得や法人との関連性が曖昧なケースでは、課税当局の目は一層厳しくなります。「見せるガバナンス」がキーワード。すなわち、適切な記録と専門家によるレビューを通じて、常に税務当局に説明できる体制を築くことが、これからの富裕層には不可欠なのです。
海外取引所・海外口座の取り扱いとCRSの影響
もう一つ、富裕層が特に注意すべきなのが「海外取引所の利用」と「CRS(共通報告基準)」です。
BinanceやBybitなど、国外を拠点とする取引所の多くは、日本の税務当局から見えづらい領域にあるとされてきました。しかし、すでに50カ国以上と金融情報の自動交換を行っているCRS(Common Reporting Standard)の枠組みにより、こうした「海外逃避」は通用しなくなりつつあります。
CRSでは、口座保有者が居住する国の税務当局に、取引情報や残高情報が報告されます。つまり、日本に居住する富裕層がシンガポールの取引所に口座を持っていても、その情報は日本の国税庁に届く仕組みになっているのです。CRS導入後、海外口座の申告漏れを理由とした税務調査件数が急増しているのは、もはや「周知の事実」といってよいでしょう。
このような背景から、海外取引所を使う場合は必ず専門家と連携し、「出所の証明」「資金の流れの透明性」を確保することが肝心です。少なくとも、「知らなかった」「聞いていなかった」という言い訳は、もはや通用しない時代に突入しています。
相続・贈与における暗号資産の取り扱い
暗号資産の税務で見落とされがちなのが、「相続」と「贈与」です。
例えば、ビットコインを大量に保有しているまま、所有者が急逝した場合。ウォレットのパスワードや秘密鍵が分からなければ、相続人はその資産を一切引き出せません。しかも、課税評価額は市場価格を基準に算定されるため、「使えない資産」にもかかわらず多額の相続税が課されるという、いわば“二重苦”に陥ることすらあるのです。
この問題を避けるには、遺言や信託などの制度を活用し、あらかじめ相続対象者にアクセス方法を伝えておく設計が必要不可欠。また、暗号資産は現物と違って所在が分かりづらいため、富裕層であればこそ、「資産台帳」や「デジタル資産一覧表」などの可視化ツールを活用するのが望ましいといえます。
贈与においても同様です。日本では年間110万円までの非課税枠がありますが、暗号資産の譲渡をもって贈与と認定されると、評価額に応じて最大55%の贈与税が課されます。「家族間だから大丈夫」という油断が、思わぬ課税トラブルにつながることは決して少なくありません。
第4章:専門家との連携と税務相談のポイント

暗号資産に精通した税理士の選び方
暗号資産の税務は、従来の株式や不動産投資とは異なる専門性を求められます。つまり、すべての税理士が暗号資産に詳しいわけではありません。特に富裕層の場合、扱う金額や取引内容が複雑になるため、暗号資産に関する「実務経験」を有する税理士を選ぶことが不可欠です。
選定の際は以下のようなポイントを確認しましょう。
- 暗号資産関連の顧客をどの程度担当しているか
- 租税回避や国際税務に対する理解・対応経験があるか
- 暗号資産に特化した会計ソフトの活用経験があるか
- 申告だけでなく、事前の設計やアドバイスも行っているか
さらに、「専門家との相性」も軽視できません。暗号資産はまだ法制度の整備が進行中の分野ですから、変化に柔軟に対応し、将来まで見据えた提案ができるかどうかが鍵になります。
税務相談で確認すべき重要事項
税務相談を受ける際、ただ「申告をお願いしたい」と頼むだけでは十分とはいえません。以下のような質問を、事前に準備して臨むことで、より戦略的な税務対策が可能になります。
- 利益が出た年に限らず、年間を通じた損益をどう管理すべきか?
- 海外取引所やウォレットの報告義務とリスクは?
- 法人での運用と個人での運用、どちらが有利か?
- 将来的に家族や子どもに承継する場合の最適な方法は?
- 税務調査に備えて、どのような記録と管理が必要か?
このような視点から相談することで、短期的な節税だけでなく、中長期的な資産防衛と成長のバランスが取れた設計が可能になります。
将来の出口戦略を見据えた設計
多くの投資家が見落としがちなのが「出口戦略」です。暗号資産は価格変動が激しいだけでなく、売却タイミングによって課税額が大きく変わるため、事前に売却シナリオを描くことが極めて重要です。
例えば、価格が上がったからといって一度に売却すると、その年の課税所得が一気に跳ね上がり、高率の税負担が発生します。逆に、数年に分けて段階的に売却することで、累進課税の影響を緩和できる場合もあります。
また、法人を活用して暗号資産を保有・運用するケースでは、法人税と所得税の差を利用した節税が可能になることも。ただし、法人活用には設立・維持コストや事務負担が発生するため、あくまで専門家との事前検討が必須です。
第5章:合法的な税務最適化戦略

節税と脱税の明確な違い
「節税」と「脱税」。言葉は似ていても、その意味はまったく異なります。節税とは、法の範囲内で税負担を軽減するための正当な行為。一方、脱税は納税義務の回避を目的とした違法行為であり、刑事罰の対象にもなり得ます。
富裕層の間では、節税テクニックとして法人設立や海外口座の活用が話題になることがありますが、これらも構造や意図次第では「脱税」とみなされるリスクがあるため、注意が必要です。たとえば、実体のない法人を使った取引や、資産を意図的に見えなくする操作は、税務調査で重加算税の対象になる可能性があります。
大切なのは、「正当な根拠に基づいた節税計画を構築すること」です。そしてそのプロセスには、税理士・弁護士・ファイナンシャルプランナーといった専門家の知見が欠かせません。
オフショア構造や法人活用の有効性
近年、香港やシンガポールなどのオフショア地域に法人を設立し、そこを通じて暗号資産を保有・運用するスキームが注目を集めています。たしかに一部の国ではキャピタルゲイン非課税のメリットがありますが、日本居住者の場合、それだけで課税を回避することはできません。
税制上の「居住地」と「実態」が一致していなければ、いくら海外法人を利用しても、国内で課税対象とされるのが現実です。また、オフショア口座や法人を利用したスキームは、CRSによってほぼ確実に国税庁の把握下に置かれます。
よって、オフショアを用いた運用は「節税対策」ではなく、「資産の分散管理」や「法規制リスクの分散」の手段として捉えたほうが現実的です。
制度改正への柔軟な対応策
暗号資産に関する税制は、年々見直しが進んでいます。たとえば、国税庁は2022年以降、法人による保有に対する期末評価課税の見直しを進めており、上場企業の暗号資産活用を後押しする動きも出ています。
こうした制度変更に柔軟に対応するには、保有資産の分散、流動性の確保、申告体制の見直しなどが求められます。将来的には、暗号資産が金融商品として制度的に整備され、「申告分離課税」の対象になる可能性もあるでしょう。そのときに慌てないためにも、日頃から情報収集と専門家との連携を欠かさないことが大切です。
第6章:成功と失敗の実例分析

匿名性に依存した結果のリスク
A氏(仮名)は、海外の匿名性の高いウォレットでビットコインを長年保有していました。価格が急騰した2021年に一部を日本円に換金し、多額の利益を得たものの、申告を行わず。ところが、CRS経由での資金移動記録が国税庁に届き、税務調査に。最終的に数千万円の追徴課税と、重加算税が科されました。
「税務はバレなければいい」という甘い考えが、資産の一部喪失という形で跳ね返った典型例といえるでしょう。
節税スキームの落とし穴
B氏は知人の紹介で、「海外法人を使えば非課税で運用できる」との話を信じ、香港法人を設立。しかし、実態はなく、すべての管理が日本国内。結果としてそのスキームは「租税回避目的」と認定され、法人の利益全額がB氏個人の所得とみなされました。
節税目的で行ったつもりが、かえって重い税負担を招いた典型例です。
専門家チームとの連携による成功事例
一方、C氏は暗号資産の保有初期から税理士・弁護士・FPで構成されたチームを組織。取引の記録を正確に管理し、海外取引についても事前に国税OBの監修を受けた申告体制を構築。相続対策として一部を家族信託に組み入れるなど、長期的視野で設計を進めていました。
結果として、税務調査もスムーズに終了。長期保有資産の一部はNFT化され、次世代への資産承継まで視野に入った“攻めと守り”のバランスが取れたモデルケースとなっています。
第7章:今後の暗号資産戦略と税務リテラシー
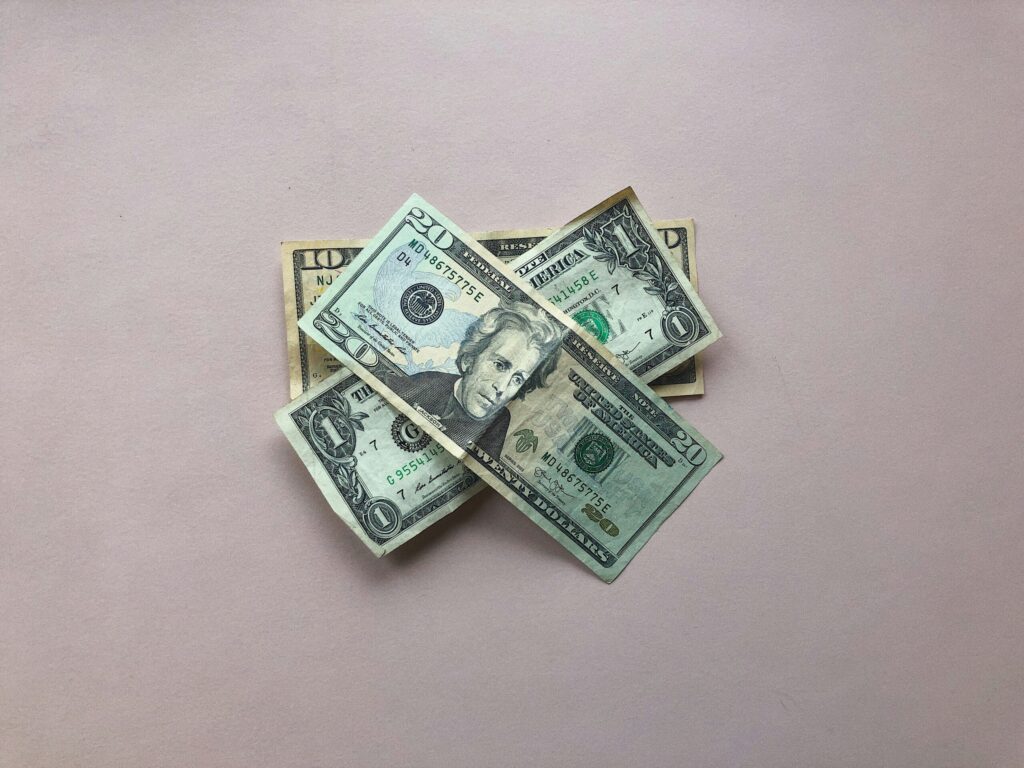
最新の法改正とガイドラインの動向
2024年現在、金融庁や国税庁は暗号資産に関する規制・ガイドラインの強化を継続中です。特にDeFi領域やNFTなど新しい金融技術への対応策が焦点となっており、税制上の扱いも流動的です。
したがって、法改正情報をキャッチアップする能力が、今後の投資家にとって“資産を守る武器”となるでしょう。
家族・事業承継における暗号資産の活用
暗号資産は、その性質上、柔軟に分割でき、国境を越えて移転可能な点が魅力です。この特性を活かして、家族信託や資産管理法人を活用した承継スキームを設計すれば、相続税対策や生前贈与の高度化にもつながります。
ただし、相続人に「知識」がなければ、その資産は“使えない宝の山”になります。リテラシー教育もセットで進めてこそ、本当の意味での資産承継といえるでしょう。
資産防衛から資産成長への視点転換
これまでの富裕層の投資戦略は「守り」が中心でした。しかし、暗号資産を含むデジタル資産の登場は、「成長」という視点を取り戻す好機でもあります。もちろん、過度な投機は避けるべきですが、リスクを適切にコントロールすれば、暗号資産は資産成長を支える柱となり得るのです。
まとめと注意点

暗号資産の世界は、常に変化とリスクに満ちています。特に税務の分野では「知らなかった」ことが大きな損失につながりかねません。富裕層にとって大切なのは、確かな知識と信頼できるパートナー、そして中長期の視点です。
暗号資産で得た利益を「真の富」に変えるためには、今こそ税務リテラシーを磨き、戦略的に備えるべきときではないでしょうか。

ファイナンス専門ライター / FP
資産運用、節税、保険、財産分与など、お金に関する幅広いテーマを扱うファイナンス専門ライター。
金融機関での勤務経験を活かし、個人投資家や経営者向けに分かりやすく実践的な情報を発信。特に、税制改正や金融商品の最新トレンドを的確に捉え、読者の資産形成に貢献することを得意とする。





